【事故解説あり】地盤事故を防ぐために知ってほしい基礎知識と対策
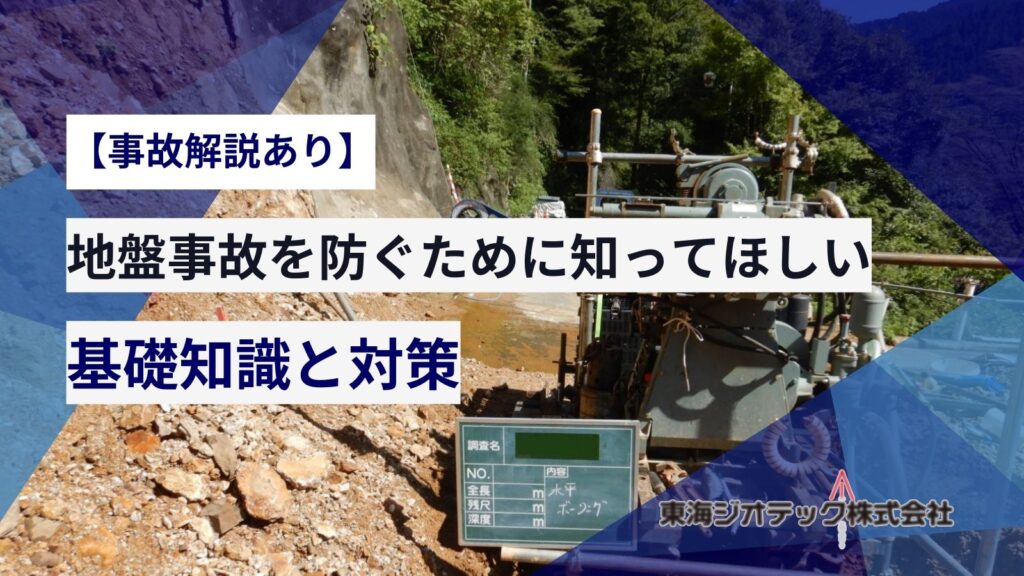
近年、異常気象による豪雨や地震により、地盤に関連する事故が日本各地で発生しています。特に東海地方では、地形や地質の特性から地盤に関するリスクが潜在的に存在しています。地盤事故は一度発生すると、人命に関わる重大な被害をもたらすだけでなく、莫大な復旧費用が必要となります。本記事では、地盤事故の実例から学び、事前の対策で防げる事故について詳しく解説していきます。
地盤事故とは
地盤事故とは、地盤の不安定さや問題によって引き起こされる事故のことです。土砂崩れ、地盤沈下、液状化現象など、様々な形態で発生する可能性があります。特に東海地方は、軟弱地盤や急傾斜地が多く存在し、地盤事故のリスクが高い地域として知られています。
地盤事故が発生する主な原因として、不適切な地盤調査、杭打ち工事の不備、盛土の施工不良などが挙げられます。これらの問題は、事前の適切な調査と対策により、ほとんどの場合で防ぐことが可能です。
近年、実際に起きた事故を例にどのような対策が必要であったかを説明していきます。
横浜傾きマンション

【事故の概要】
2014年10月、横浜市都筑区に三井不動産レジデンシャルが販売した全4棟705戸の分譲マンション『パークシティLaLa横浜』で全4棟705戸の分譲マンションのうち1棟の渡り廊下の手摺りがずれていることから発覚し、最大で約20センチ傾きが確認されました。その後の調査で、50本の杭のうち8本が強固な地盤(支持層)に達していなかったことが判明、三井住友建設の二次下請けになる旭化成建材が杭打ち施工に必要な地盤データの改ざんを行っていたことが明らかになりました。
この事態により、705世帯もの入居者が退去を余儀なくされ、住民の生活基盤が根底から揺らぐ深刻な事態となりました。 また、このようなデータの改ざんはこの「パークシティLala横浜」だけではなく、全国で約300件ものデータ偽装の疑いがあり、このようなデータ流用が業界で広く行われていた事が、建設業界を揺るがす大きな社会問題となりました。
【事故の原因】
この事故の根本的な原因は、以下の複数の重大な問題が重なり合った結果でした
1・不十分な地盤調査
この地域は埋立地であり、地盤が変動しやすい特性を持っていたにもかかわらず、実施されたボーリング調査の本数は必要最低限を下回っていました。
そのため、地層の変化を正確に把握することができず、場所によって大きく異なる支持層の深さを見落としてしまう結果となりました。
さらに、埋立地特有の地盤特性を考慮した詳細な調査も行われておらず、建物を支える地盤の状態を的確に評価できていませんでした。
2・杭打ち工事の重大な不備
杭打ち工事においても重大な不備が次々と明らかになりました。
調査の結果、50本の杭のうち8本が強固な地盤(支持層)に達していなかったことが判明、杭打ち施工に必要な地盤データの改ざんや、杭の打設位置や深さが設計図面の指示通りに施工されていない箇所が多数確認され、基礎工事全体の信頼性が大きく損なわれる事態となりました。
3・品質管理体制の欠陥
この事故の背景には深刻な品質管理体制の欠陥が存在していました
施工管理者が現場での確認作業を適切に行っておらず、工事の品質を担保するための基本的な管理が機能していませんでした。
また、施工データの偽装が行われていたにもかかわらず、それを発見できなかった検査体制の不備も明らかになりました。
これらの問題の背景には、工期短縮やコスト削減を優先せざるを得ない現場の状況があり、そうした圧力が結果として品質管理の軽視につながった可能性が専門家から指摘されています。
この事故は、建設業界に大きな衝撃を与え
- 地盤調査は建物の安全性を確保する上で最も基本的かつ重要な工程であること
- 特に地盤条件が複雑な場所では、十分な数のボーリング調査が不可欠であること
- 施工データの信頼性を確保するための厳格な管理体制が必要であること
- コストや工期の制約を理由に、安全性に関わる調査や工事を軽視してはならないこと
など、重要な教訓をもたらしました
この事故を契機に、建設業界では地盤調査の重要性が再認識され、施工管理体制の見直しが進められました。また、マンション建設における地盤調査や杭打ち工事の基準が厳格化され、第三者による検証制度の導入なども進められています。
このような深刻な事故を二度と繰り返さないためにも、私たちは適切な地盤調査の実施と、その結果に基づく確実な施工の重要性を、改めて認識する必要があります。
博多駅前道路陥没事故・埼玉県八潮市道路陥没事故

【事故の概要】
2016年11月8日午前5時15分頃、福岡市博多区の博多駅前で突如として巨大な陥没が発生しました。この陥没は幅約27メートル、長さ約30メートル、深さ約15メートルという、都市部での陥没事故としては国内最大級の規模となりました。繁華街の中心部での事故でしたが、早期発見と迅速な避難誘導により、幸いにも人的被害は発生しませんでした。しかし、周辺の商業施設や交通機関への影響は甚大で、都市機能が一時的に麻痺する事態となりました。
【事故の原因】
この事故は、地下鉄七隈線延伸工事に伴う掘削作業中に発生しました。直接的な原因は、地下水の予期せぬ流入により周辺地盤が緩んだことでしたが、より本質的な問題として、地質調査の不十分さが指摘されています。
特に以下の点が重要な問題として挙げられています。
1・地質調査の不足
工事区間の地質構造が複雑で、支持地盤が波打っているような状況でしたが、ボーリング調査の本数が十分ではありませんでした。
地層の不連続性を詳細に把握できていなかったことで、地下水の流れを正確に予測できていませんでした。
2・工期・コスト優先の姿勢
工事の効率性やコスト削減が優先され、詳細な地質調査に十分な時間と予算が割かれていませんでした。
また、地質リスクの重要性が工事関係者間で十分に認識されていない状況がありました。
3・リスクマネジメントの不備
地質リスクに対する組織的な管理体制が不十分で、予期せぬ事態に対する対応策が事前に十分検討されていませんでした。
この事故を契機に、
- 地質調査は工事の安全性を確保する上で必要不可欠な投資であり、決してコストカットの対象とすべきではないこと
- 複雑な地質構造を持つ地域では、十分な数のボーリング調査が必要であること
- 行政工事に限らず、民間工事においても適切な地質調査と地質リスク管理が重要であること
など、建設業界全体で地質リスクマネジメントの重要性が再認識されることとなりました。
なお、この事故の復旧工事は驚異的な速さで進められ、わずか1週間で道路は再開通しましたが、この迅速な復旧は決して地質調査の軽視を正当化するものではなく、むしろ事前の十分な調査と対策の重要性を示す事例として、建設業界に大きな教訓を残しています。
また、2025年1月28日には埼玉県八潮市の県道交差点において、道路が突如として陥没し、通行中の大型トラックが転落するという深刻な事故が発生しました。陥没の規模は幅約8メートル、長さ約12メートル、深さ約5メートルに及び、事故発生から4週間が経過した2月25日現在も、転落したトラックの運転手の安否が確認できていない状況が続いています。
【事故の原因】
この事故の詳細な原因は現在調査中ですが、道路の地下に埋設された下水道管が経年劣化により破損し、破損部分から土砂が徐々に流出し、地下に空洞ができたと考えられています。
日本の下水道インフラの老朽化問題
この八潮市の事故は、日本全体が直面している深刻なインフラ老朽化問題の一例といえます。国土交通省の調査によると、日本の下水道管の総延長は約47万キロメートルに達しています。これはおよそ地球の11.7週分にも該当し、このうち標準耐用年数50年を経過した管渠の延長は約2.1万キロメートル(約4%)となっています。 さらに、今後20年間で標準耐用年数を超える管渠は約10万キロメートルに増加すると予測されています。
事故を事前に防ぐことはできたのか?
地下の空洞を事前に見つけ、破損した下水道管を修繕できればこうした陥没事故を未然に防ぐことはできます。
しかしながら、地下埋設物の経年劣化は目視での確認が難しく、空洞を調べる手段として は地中に電磁波を照射し、その反射波の画像を解析する「地中レーダー検査」が一般的に行われていますが、この検査では深さ2mまでしか調査をすることができません。
今回、事故のあった埼玉県八潮市の事故現場は地下10メートルもの深さに下水道管が埋設されている特異なケースでした。
このため、通常の地中レーダーによる空洞調査を行っていたとしても、今回の陥没を予測することは不可能であったと考えられます。
参照:【八潮・道路陥没】露見した下水道の盲点…深さと地盤改良、危ないのは高度成長期にできた都市部の住宅街や国道付近
このように深い位置での空洞調査を行うにはボーリング調査や下水道管内部を専用カメラで確認する「TVカメラ調査」などを組み合わせた総合的な調査が必要となります。
しかしながら、地球約11.7周分にも及ぶ膨大な下水道管を、ボーリング調査やTVカメラ調査だけで網羅的に点検することは、技術的にも費用面でも現実的ではありません。
国土交通省の試算によると、今後30年間で必要となる下水道施設の更新費用は総額約130兆円にのぼるとされています。
今後の課題
埼玉県八潮市の道路陥没事故のような事例を見ると、地下空洞や埋設管の異常を事前に発見することの難しさと重要性が改めて浮き彫りになります。
インフラの老朽化は日本全体が直面している課題であり、こうした事故を未然に防ぐためには、国と地方自治体、そして民間企業が連携し、計画的な調査と維持管理を進めていくことが重要です。
私たちは八潮市の事故のような痛ましい事例を教訓とし、地下の見えない危険を可視化する技術と知見がさらに発展し、どんな場所でも事前に適切な調査ができる社会になることを願っています。
熱海市伊豆山土石流災害

事故の概要
2021年7月3日午前10時30分頃、静岡県熱海市伊豆山地区で大規模な土石流が発生しました。この災害により27名の尊い命が失われ、1名が行方不明となる痛ましい事故となりました。約54,000立方メートルもの土砂が一気に流出し、土石流は約2キロメートルにわたって建物や道路を押し流し、98棟の建物が全壊・半壊・一部損壊するなど、甚大な被害をもたらしました
事故の原因
この悲惨な災害の主な原因は、盛土造成地の不適切な施工管理にありました。逢初川上流部に2007年から2011年にかけて行われた盛土は、高さ約50メートル、幅約100メートルにも及ぶ大規模なものでしたが、適切な基準で施工されていませんでした。
具体的な問題点として以下が明らかになっています.
- 盛土の締固めが不十分で、土の強度が確保されていなかった
- 排水施設が適切に設置されておらず、盛土内に大量の水が溜まりやすい状態だった
- 土砂の中に木くずなどの不適切な建設残土が混入していた
- 盛土の傾斜が急すぎる箇所があった
特に重要な問題として、静岡県の行政対応の不備も指摘されています。県は盛土の危険性を認識していながら、強制力のある実効的な対策を取らなかったことが明らかになりました。当時の静岡県には盛土を規制する条例がなく、行政指導という形でしか対応できなかったことも、この事故を防げなかった要因の一つでした。
この災害を教訓として、静岡県は2022年7月に「盛土等の規制に関する条例」を制定。この条例では、盛土等の許可制の導入や、不適切な盛土への是正命令、罰則規定の強化などが定められました。
さらに、この事故の影響は全国に波及し、
- 千葉県:新たな盛土規制条例を制定
- 神奈川県:盛土条例を改正し、規制を強化
- 愛知県:盛土の監視体制を強化
- 国レベルでは「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が2022年5月に成立
など、各地で盛土規制の見直しが進められました:
この痛ましい事故は、適切な地盤調査と盛土管理の重要性を改めて社会に示すこととなり、全国的な法整備のきっかけとなりました。地盤に関する事前調査や施工管理を軽視することが、どれほど深刻な結果をもたらすかを私たちに教えてくれました。
東三河集中豪雨

事故の概要
東三河地域は、地形的な特徴と気象条件が重なり、集中豪雨による災害が頻発しています。特に2020年から2023年にかけては、時間雨量100ミリを超える豪雨が複数回発生し、各地で深刻な被害をもたらしました。急傾斜地での土砂崩れは住宅地にも被害を及ぼし、また軟弱地盤地域では地盤沈下により道路や建物に重大な損傷が生じています。豊川や柳生川などの河川流域では、氾濫による浸水被害も度々発生しており、地域の安全性に大きな課題を投げかけています。
事故の原因
東三河地域における災害の原因は、自然的要因と人為的要因が複雑に絡み合っています。
まず、地形地質的な特徴として、この地域には急傾斜地が多く存在しています。特に中山間地域では、花崗岩が風化してできたまさ土(真砂土)が広く分布しており、この土は雨水を含むと極めて不安定になりやすい特性を持っています。また、地質構造が複雑で、岩盤の亀裂や断層が多いことも、地盤の不安定性を高める要因となっています。
さらに、近年の都市開発による影響も深刻です。山林の開発や宅地造成により、本来の自然地形が持っていた排水機能が失われつつあります。雨水を徐々に地下に浸透させ、河川に流す自然の排水システムが分断されることで、豪雨時の地表水の集中や地下水位の急激な上昇を引き起こしています。こうした変化が、土砂災害や地盤災害のリスクを一層高める結果となっています。
特に問題となっているのは、過去の開発時期に行われた地盤調査や対策工事が、現在の気象条件を想定していなかった点です。近年の気候変動により、従来の想定を超える規模の豪雨が頻発するようになっており、既存の防災施設や対策工事では十分な対応ができない状況が生まれています。
これらの課題に対して、東三河地域では
- 詳細な地質調査に基づくハザードマップの更新
- 既存の擁壁や法面防護工の再点検と補強
- 雨水浸透施設の整備による自然な排水機能の回復
- IoTセンサーを活用した地盤変位の常時監視システムの導入
など、様々な取り組みが進められています。
地域の安全を確保するためには、過去の災害から得られた教訓を活かし、地域特有の地形地質条件を十分に考慮した防災対策を実施していく必要があります。特に新規の開発においては、事前の詳細な地盤調査と、それに基づく適切な対策工事の実施が不可欠です。
事故を起こさないための対策とは
地盤事故を防ぐためには、まず専門家による適切な地盤調査の実施が不可欠です。
これには、ボーリング調査、標準貫入試験、ラムサウンディング試験などが含まれます。
特に東海地方の地盤特性を考慮すると、建設予定地の地質構造を正確に把握することが重要です。
地盤調査では、支持層の深さ、地下水位、土質の性状、液状化の検討などを詳細に調べる必要があります。
また、盛土工事を行う場合は、適切な締固めと排水施設の設置が必須です。定期的な維持管理と点検も重要な対策の一つとなります。東海ジオテックでは締固め試験はもちろん、静岡県盛土条例に対応した土壌分析や調査も提供しています。
地盤調査の方法として、私たちは標準的なボーリング調査に加え、より効率的で経済的なラムサウンディング試験も提供しています。
費用対効果の高いラムサウンディング試験は、予備調査や補完調査として非常に有効な手段となっています。
国土交通省が定める土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドラインについて
国土交通省は、地盤リスクを適切に管理するためのガイドラインを策定しています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000681.html
国土交通省は、地盤リスクを適切に管理するためのガイドラインを策定しています。
このガイドラインでは、事業の各段階におけるリスクマネジメントの重要性が強調されています。
計画段階では、地形・地質条件の確認と概略的な地質リスクの抽出が求められます。設計段階では、詳細な地質調査と対策工の検討が必要です。施工段階では、継続的なモニタリングと計測管理が重要となります。
まとめ
地盤事故は、適切な事前調査と対策により防ぐことができます。
地域特有の地盤特性を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
私たち東海ジオテックは、ボーリング調査から空洞調査まで、総合的な地盤調査サービスをワンストップで提供しています。
調査費用を節約することで、後に大きな損失を被るリスクを負うことは避けるべきです。
安全な建築物と災害に強いまちづくりのために、専門家による適切な地盤調査と対策の実施が不可欠です。
確かな技術と経験に基づいた調査で、皆様の安全な暮らしをサポートしていきます。

